◆都市診断
戦後50年の1995年は日清戦争100年にも当たる。 ─ 「窓をあければ港が見える」と歌われるミナトの情緒がみなぎる小樽は、海から生まれ、海と共に育ち、海に生きる星の下に生活している。 ── 小樽開基100年記念式典開催の前年に当たった1964(昭和39)年4月、北海道新聞年間企画『都市を診断する』第4回目、「小樽」の書出し部分である。
学芸部記者として、北海道都市学会の学者先生たちと道内各市を順繰りに回っていた。成果は都市学会監修の単行本になって1966年に、東京・誠信書房から『都市診断 北海道編』として出版された。
「 ─ 北海道の小樽というより“日本の、世界の小樽”だった時代があった。かつての栄光を胸に秘め、現在の逆境?に耐えながら“昔日の躍進再び”と精進する元チャンピオンか。あるいは功成り名遂げて仕事は次代に譲り、第一線を退いたご隠居さんなのか。
─ 小樽は城のない城下町である。この城下町には殿様が何人もいる。道内都市には中世がない。そこには古いたたずまいを思わせる城下町のふんいきは生まれないが ─ 」と続く。
30年も前の記事なのに、なぜか今でも通用しそうだ。そこが小樽らしさであり、小樽の短所は長所にもなる。
◆五港貨物の動き
「樺太、函館、東京、根室への定期航路は明治6年に開かれ、8年の入港船は666隻だったのが、13年には5,358隻と10倍になり、大正12年の入港船は神戸、横浜、下関、門司に次いで全国第5位。関門連絡船を除けば神戸、横浜と肩を並べる日本の3大港の1つになっていた。 ─ 」
港を道内と本州との関連で見たのが、表1の5港府県貨物移出入額である。8年実績を100と基準にした指数にすると、伸び率が一目瞭然になる。福山こと松前と江差、寿都と軒並み10年では減少しているのは、明治初年の混乱期だったから。14年の構成比では、函館が65%と断然強く、小樽12%、江差11%、福山6%、寿都5%の順。
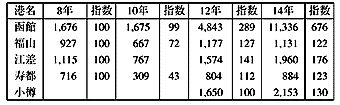
本州との関係では、入口に当たる函館が断然有利な事は言うまでもない。明治14年までに7倍近く増え、全道の6割をしめ590万円の移入超過になっている。この時代の本州商品は、一度函館に入ってから道内各地に運ばれた。函館は名実ともに北海道の玄関口で、全道が後背地、商圏になっていた。
◆港が必要
平地が少ない小樽が商人のまちになるには、どうしても港が必要だった。天然の良港だとしても、北西の風は石狩湾からストレートに港の奥まで吹き付ける。明治26年冬の嵐は湾内に大被害を出した。英・蘭の外国技術者からの設計案なども出たが、日清戦争で先送りされてしまい、道庁予算が付いて北防波堤工事が始まったのは30年5月だった。
当時東洋ではスリランカのコロンボだけ、と言われた波の激しい湾内での築港は難工事続きになった。途中31年12月に大時化に見舞われて失敗したかと思われたが、日本初の火山灰混入コンクリート使用など、独特な新技術の導入などもあってどうやら完成する。
最大工事だった北防波堤が年ごとにジワジワと海中に伸びて行く様子は小樽そのものの成長を示しているようだった=表2。達成率を見ると、35年ごろからピッチが上がっている。総延長4,255尺、1,300メートルの防波堤の完成に、11年間で172万5,000円も費用をかけた。メートル当たり1,300円以上。付帯工事を含めて221万円もの税金を使った計算になる。
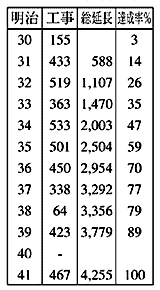
◆修築計画図
図1は小樽市史の「小樽港修築計画図」で、明治27年実測、29年3月に作成した。海岸線に沿って詳細な描写が見られ、立岩、手宮鉄道桟橋の位置に港内の水深が細かく記されている。図の左側に伸びるのが第一次工事の北防波堤。その先に点線で描かれるのは島防波堤で、平磯岬からの南防波堤計画はまだ無かった。
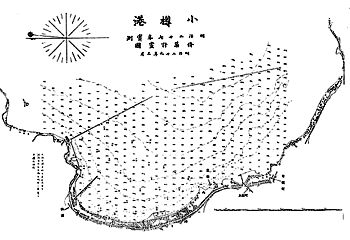
平磯岬下の若竹トンネル用の土砂を使って埋立てた築港地区の広場は防波堤工事用地になり、海に沈めるコンクリート・ブロックを製造した=写真1。製造したブロックを防波堤の敷設現場まで運ぶのも大仕事だった。写真2は蒸気動力の特種作業機。レール上を移動し、ブロックをつり下げてゆっくりと沈めて行く。

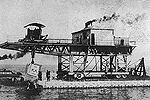
ケーソンと呼ばれた巨大なコンクリート製の箱を沈めるシーンは壮大な見モノだったから、現場近くに小船で見物する人も多かったそうだ=写真3。

手宮の烏帽子岩から海中に伸びた北防波堤は明治41年に完成。続いて南端の平磯岬からの第2防波堤工事が始まり、南北両防波堤が完成したのは大正10年だった。写真4は、築港側から始まった南防波堤工事現場。北大図書館にある「小樽築港の模様」もこの時期の工事現場のようだ=写真5。平磯岬下から伸びる南防波堤の様子がよく分かるのが写真6。右側が築港、防波堤基部の先に東小樽海水浴場、その先が朝里。



