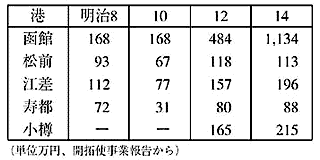◆急速な内地化が進む
江戸幕府の大政奉還から、京都政権の東京遷都に至る明治維新は、蝦夷地改め北海道にとっても、一大転換期に当たった。幕藩体制下の松前地は本州とは別の、“外地”の世界で、主たる住民は和人と呼ばれた日本人とは別の蝦夷と呼ばれた先住民族アイヌだった。こうした蝦夷地の時代から、政治・経済の両面に加えて生活・風俗の面からも、急速な「内地化」が進められた。
つまり、蝦夷地という名の『異国』イコール「外国扱い」から、東京政府直属の『開拓地』とされたわけだ。1869(明治2)年8月15日に、蝦夷地を『北海道』と命名したということは、この島はもはや異国ではないといった意味での「日本の本土化宣言」である。
だから、各省大臣と同格の長官がいる開拓使が設けられた。しかしまだ開拓地だからと、なにかといえば本州とは違った、特別扱いの諸制度が実施される。
武士階級を廃止し、国民皆兵の理念から全国的に徴兵制を敷きながら、さしあたって本道だけ、その適用を除外した。まだいわゆる皇民化が進んでいない、との理由だった。学生だった夏目漱石が、東京から岩内に本籍を移した理由が、徴兵逃れだといわれるのは、その1つの例になる

吹上町17浅岡家跡(昭和50年当時)
「文豪夏目漱石立籍地」の碑が後志管内岩内町の吹上町17浅岡家の跡地に立っている=写真1。漱石の戸籍が浅岡家に移されたのは明治25年4月5日で、浅岡は岩内にあった三井物産出張所の御用商人だった。徴兵逃れに戸籍を移したのは父親、家が絶えてしまうのを心配しての行為だという。のちに総理大臣になった浜口雄幸も、網走管内湧別町に戸籍を置いていたそうだ。
徴兵令の本道適用は、札幌に第7師団が創設された明治29年から。まず開拓が進んでいた道南の渡島・後志・胆振・石狩の四国を対象にし、2年後に全道に適用を拡大した。
◆銭函から全道に号令
明治2年10月12日、島判官が銭函に新設されたばかりの開拓使仮役所に着任する。長官不在のまま、ナンバー2だった島義勇は、銭函に居座って全道に号令を発する。島が赴任と同時に設置した手宮海官所は、その後の小樽商業発展のきっかけをもたらした。
場所請負制の廃止は、請負人を漁場持と名称を変えただけに止まらない。幕府の運営自体が重農抑商政策では成り立っていかないことに気付いたのは、8代将軍吉宗による享保改革のころからだろう。続く田沼意次時代の問屋・株仲間の育成強化策は、商業利得を商人に独占させず幕府が直接握ろうと意図したものだった。
田沼は、当時の日本に残された処女地としての北海道に目を付け、いわゆる“天明の蝦夷探検”を企てるが、政権寿命が短く時代も早すぎて果たせず、開拓という名の「内国植民地化」は、100年後の明治時代にその華を咲かせることになる。
場所請負制は軍事力を持つ藩権力をバックにした請負商人が、場所内の行政司法権まで行使し先住民を酷使しての利潤追及の自由を保証した。欧米列強の拡大主義にさらされ、廃藩置県を強行して近代化を押し進めようとした明治政府が、こうした異常ともいえる体制を本州府県並みにしようとしていた北海道に残す訳がない。
◆場所請負廃止と海官所設置
松前藩に代わった開拓使が北海道経営のため発足早々に手掛けた施策は、場所請負制度の廃止と海官所設置だった。いずれも商港を目指していた小樽の将来に強い影響を与えた。
海官所は従来の松前・箱館・江差3港にあった沖ノ口役所が持っていた機能を受け継ぎ、箱館・寿都・幌泉と手宮の4港に設けられた。松前藩の収入は沖ノ口役所からの税金が大半を占めていた。当時は維新直後なので、松前・江差地方は松前藩改め館藩の領地だったから、開拓使の管轄外。このため、当初は松前と江差を除外していたが、地元側からの陳情もあって翌3年1月に両港にも海官所が設置された。こうした混乱期の事情も、小樽にとっては有利に動いた。
海官所の仕事は、移出入税や停泊税、船税を取るほかに、船の鑑札、旅人の取締も扱った。3年に海関所、8年に船改所と次々に改称したので、資料によって名称が異なり、混乱してしまう。えりも岬に近い幌泉は気象条件が悪く、船泊りに難があったので室蘭・厚岸に移っている。この時期の小樽港の状況を示す写真がある。
◆信香常夜灯
明治4年に手宮海関所が277両の大金を使って「信香常夜灯」を信香町の丘の上に建てた。水面から2丈6尺というから約8メートル、当時としては高価なガラス張りだった。慣れない海域で夜間航行する船にとって、正に暗夜の灯だっただろう。写真2は、手前の浜に漁家と魚干場があって、海に突き出た丘の海側斜面に下部が黒く塗られ、白い灯台が上に載る常夜灯が見える。常夜灯の場所は、序章の図3「小樽最古の市街見取り図」では丘の向こう側に郡役所がある、#印の場所辺りだろうと思う。

この常夜灯は完成後僅か3年の7年5月に焼失し、ついに復活せず。この時期の入港船は、昼間に限り水天宮丘下の海岸に目立った立岩を目当てにしたという。明治11年7月に函館から海路小樽にやって来たアメリカ人学者が、海から見た小樽の情景をスケッチしている=図1。前年に来日し、横浜から東京への車窓から大森貝塚を発見したことで有名なF・S・モースであり、「妙な形の岩が記念碑みたいに、水面からつっ立っている。顕著な岩のあるものの写生」(右)、「石造の埠頭から見た景色」(左)との説明が付く。

◆目印は立岩
この石造埠頭は明治6年に初めは木造で作られた色内埠頭で、幅が11メートル、長さは310メートルを越した。経費は3,324円もかかったが、7年10月に大時化で大破してしまう。代わりに10年11月に6,000円をかけた手宮桟橋が完成し、さらに13年8月には鉄道工事のために規模を拡大している。
史談会編集の『写真集小樽』の冒頭に「小樽の黎明」、“明治初年の立岩沖”の説明で、日本画風の写真3が載っている。沖の3隻はいずれも3本マストの洋式帆船であり、当時は主流だった1本帆柱の和船が1隻も見えないのはなぜだろう。

小樽入港船のための灯台は、札幌県が高島郡祝津村の日和山岬に設置する明治16年まで待つことになる。海面からの高さ41.5メートルの日和山灯台は建設費6,603円。灯台完成まで、入港船は岬の根元にある赤岩だったという。
海官所が設けられたことで、港の後背地からの産物送り出しが便利になる。本州だけでなく、外国との交易のチャンスも生まれる。明治政府の出先機関である開拓使の札幌本府に近い、という地理的条件も手伝って、伊豆の下田とともにいち早く開港していた函館と肩を並べる商港に育ってゆく。この時期に、松前地方から小樽へ、かなりな商人たちが移っている。
海官所設置に伴い、福山と江差の問屋に対し、手宮と寿都での新規開業を、開拓使函館出張所が呼び掛けたら、福山の16人、江差の13人が全員希望したという。もちろん財源のない開拓使がただで、というはずがない。問屋開業に必要な株の許可条件は、開拓使への献金500両だったという。つまり手宮問屋株は500両。当時の金で500両という大金をポンと払えるような大金持たちが、新興勢力の東京政府出先機関によって、小樽に引っ越してくる。
◆大金持ちがやって来る
明治3年春の第一陣に京屋・桂吉左衛門、阿部屋・村山利兵衛、同・村山唯五郎、同・張江玉五郎らが。この年の冬になって、塩越屋・工藤庄兵衛、阿部屋・張江利左衛門、大津屋・田中武左衛門、河田屋・富永増右衛門、種倉屋・塩田次左衛門といった有力な松前商人らが次々とやって来た。
小樽商人では初代名主の山田兵蔵と文治が問屋開業に応じ、問屋頭取に任命された村山唯五郎、桂吉左衞門らは小樽では新参の松前・福山商人だった。問屋はその港に永住することが第1条件だったから、村並になったばかりの小樽へ一家挙げての移住に迫られる。いくら、商売のためとはいいながら、長年住み慣れた、歴史ある城下町からの引っ越しは大変だったろう。しかし、こうした大商人の移住が、その後の小樽のたたずまいに大きな影響を与えたことは明らかだ。
高島場所請負人だった西川家は明治12年に松前支店を閉鎖して忍路運上屋跡を総支店に、高島運上屋と小樽堺町に分店を置いている。
◆北前船が支える
この時代の商港小樽は、日本海航路を走る北前船が支えた。松前藩時代は、場所請負商人が北前船のスポンサーだった。1本帆柱の和船が風にまかせて、年に1回ずつ裏日本から瀬戸内経由で大阪まで往復航海した。開拓使が請負制度を廃止しても、しばらくの間、本州各地との交易は北前船が主役を勤めた。
北前船は北国回船とも呼ばれ、北国・東北地方から上方への西回り回船。積み荷の運賃制でなく、寄港する各地の産物を買い込んで、自己責任で売買するのが特質だった。米を主体に四十物(あいもの)と呼ばれた塩魚や干し魚、昆布などを上方に運んだ。四十物という姓名は道内でも珍しい部類だが、まま見られる。
北前船は寄港地の商取引を活発化し、運搬業というより問屋の性格が強かった。小樽市博物館のガラスケースに、高田屋嘉兵衛の辰悦丸模型が飾られる=写真4。

北を上に置く一般的な地図からすると、瀬戸内を通り大阪へ行く北前船の西回り航路よりも、江戸回りの方が近道みたいな感じになる。しかし、東を上に地図を回して見ると、日本海を通る道が実際は近道になっていることに気付く=図2。さらに内海の日本海の方が海が荒れず、帆船にとっての航海は安全そのものだった。地図は必ず北が上とは限らない。松浦武四郎地図は反対に北が下になっている。
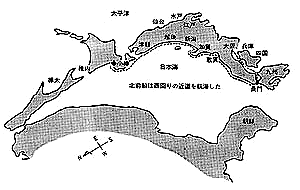
明治10年代で、24反千石積みの帆船が一航海で行き150円、帰り850円、合わせて1,000円の収益を上げ、諸雑費を引いた純益が280円だったという。同時期で東京・大阪間を年6回も往復しながら、純益が170円の阪神地方船主より3倍以上の稼ぎをしていた、と牧野隆信著『北前船』に研究報告が載っている。
幕末期の1857(安政4)年の海産物移出先状況を見ると、加賀・越中・越前・能登向けといった西回りの船荷が、南部・仙台・江戸への東回りの2倍半に及ぶ。さらに西回りの終点、大阪や兵庫は途中の加賀・越前の3倍に達している=表1。
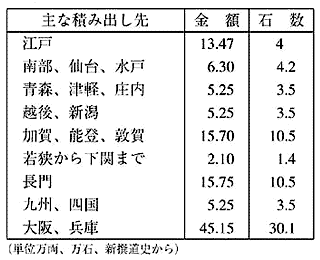
◆典型的な植民地経済
明治8年、本州への移出は248万円で移入が195万円。それが14年になると、移出704万円、移入1,232万円と、膨れ上がる。実に528万円の移入超過になった。その内訳を見ると、移出の88%が水産物、移入は繊維・雑貨・酒といった日用品が63%、米などの農産物が30%。原料輸出・製品輸入、しかも金額面からは著しい輸入超過という典型的な植民地経済になっている。また、こうした移出・移入品目が、小樽商人の主要取扱品目と一致していることは、当時の小樽が置かれた状況からも当然といえよう=表2。
開拓使は明治15年に「使命を果たした」と称して無くなる。このころ、政府の殖産興業政策なるものが背景にあって、北前船は最盛期を迎えていた。
北前船が結んでいた本州は、太平洋沿いでなく、日本海経由の裏日本だったということが、戦後の地盤沈下と関係してくる。小樽の街が形成され、そこに働く商人たちの仕事場が広がってくれば、次はお互いの利便を図るための会議所が生まれることになる。